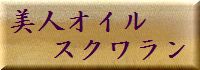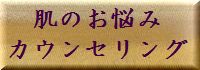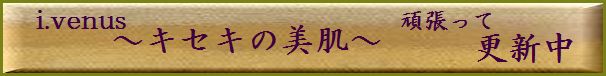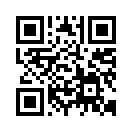2013年11月18日
2013年10月31日
背筋も凍る双龍図 「狩野派と橋本雅邦-そして、近代日本画へ」展
狩野派の絵師であった橋本雅邦。
明治維新という文化の価値観の大きく変わった時代に、
大和絵を近代日本画へと導いた橋本雅邦。
その足跡をたどった展覧会に
埼玉県立歴史と民俗の博物館に行って来ました。
絵画と言えば大和絵。十二一重、御所車の世界。
繊細で美しい美人画。大好きですゥ~
狩野養信 「源氏物語子の日図屏風」(右隻)遠山記念館蔵

まぁ、つい最近描かれたかのように鮮やかな色彩。
美しい~
ガラスさえなければ…おでこをくっつけて観てきました。
何より凄い迫力だったのが、双龍図屏風。
光を落とした展示室に浮かび上がる金屏風。
そこに墨で描かれた龍が今にも動き出して向かって来そうな迫力。
思わず背筋がゾッとしました。
今まで観た龍の絵の中で、一番の迫力でした。

政権が変わり、西洋文化の流入と共に日本文化が否定された時代。
一時は油絵を描きながらも、東京美術学校の教師として、
横山大観などの後進を育て近代日本画を確立した橋本雅邦画伯。
お蔭さまで、今でも美しく繊細な日本画を観ることが出来ます。
四季と共にあった日本人の感性は、本当に繊細で美しい。
明治維新という文化の価値観の大きく変わった時代に、
大和絵を近代日本画へと導いた橋本雅邦。
その足跡をたどった展覧会に
埼玉県立歴史と民俗の博物館に行って来ました。
絵画と言えば大和絵。十二一重、御所車の世界。
繊細で美しい美人画。大好きですゥ~
狩野養信 「源氏物語子の日図屏風」(右隻)遠山記念館蔵
まぁ、つい最近描かれたかのように鮮やかな色彩。
美しい~
ガラスさえなければ…おでこをくっつけて観てきました。
何より凄い迫力だったのが、双龍図屏風。
光を落とした展示室に浮かび上がる金屏風。
そこに墨で描かれた龍が今にも動き出して向かって来そうな迫力。
思わず背筋がゾッとしました。
今まで観た龍の絵の中で、一番の迫力でした。

政権が変わり、西洋文化の流入と共に日本文化が否定された時代。
一時は油絵を描きながらも、東京美術学校の教師として、
横山大観などの後進を育て近代日本画を確立した橋本雅邦画伯。
お蔭さまで、今でも美しく繊細な日本画を観ることが出来ます。
四季と共にあった日本人の感性は、本当に繊細で美しい。
2013年10月10日
特別展お江戸で京都の歴史を観る
蒔絵のお稽古の後、足をのばして特別展・京都に。
国宝・「洛中洛外図屏風」と二条城障壁画を観てまいりました。
「洛中洛外図屏風」は、昨年サントリー美術館で
デジタル化されたものを拡大したりして楽しみましたが、
今回は「本物」です。
戦国末期から江戸初期の京都の街並み。
そこで暮らす貴族から庶民の姿までが、活き活きと描かれております。

竜安寺の枯山水の石庭。四季の移ろう様を超高精細映像4Kでリアルに再現。

そして、ニューヨークからの里帰りの「列子図襖」

最後に二条城の黒書院を再現した障壁画の数々。
狩野探幽筆の「松鷹図」は迫力の15面。
二条城に行っても複製しか観ることはできません。

まさに!権力の象徴。迫力があります。
描く題材によって、描く絵師たちの階級も分かれるそうです。
高貴な人を描くのは、上級な絵師。
明治維新で世の価値観が変わってしまい、
多くの書画、骨董などの美術品が海外に流出してしまったのは残念ですが、
全く不明になったり失われるよりは、
何処でも大切に保存されているのは、有り難い事と思いました。
国宝・「洛中洛外図屏風」と二条城障壁画を観てまいりました。
「洛中洛外図屏風」は、昨年サントリー美術館で
デジタル化されたものを拡大したりして楽しみましたが、
今回は「本物」です。
戦国末期から江戸初期の京都の街並み。
そこで暮らす貴族から庶民の姿までが、活き活きと描かれております。

竜安寺の枯山水の石庭。四季の移ろう様を超高精細映像4Kでリアルに再現。

そして、ニューヨークからの里帰りの「列子図襖」

最後に二条城の黒書院を再現した障壁画の数々。
狩野探幽筆の「松鷹図」は迫力の15面。
二条城に行っても複製しか観ることはできません。

まさに!権力の象徴。迫力があります。
描く題材によって、描く絵師たちの階級も分かれるそうです。
高貴な人を描くのは、上級な絵師。
明治維新で世の価値観が変わってしまい、
多くの書画、骨董などの美術品が海外に流出してしまったのは残念ですが、
全く不明になったり失われるよりは、
何処でも大切に保存されているのは、有り難い事と思いました。